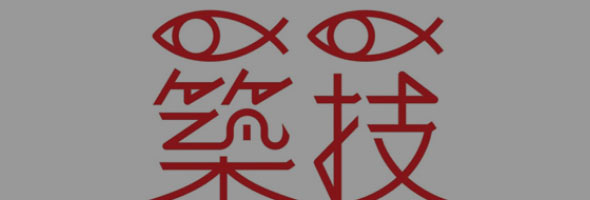築地を知る | 築地昔話館 | 男たちの語り
隣近所、順番に七輪が回る町
吉江嘉市さん・梅子さん(大正9年・昭和6年・吉江商店)

先代が日本橋で始めた日本橋料理道具店は関東大震災後、芝浦を経て、昭和13年に築地場外市場の現在地に移転した。 そのとき、嘉市さんは16歳だったが、4年後には戦争へ。
「あの戦争のどさくさで、当時の築地の思い出などは忘却の彼方だよ。戦争から戻ってきたのが、終戦の8月15日を過ぎてから。 疎開している人が多く、うちも親父が店を閉めて千葉の田舎に行っていました。あの頃は県外から東京へ入れなかったんですよ。 こっちに戻ってきても一日の米の配給が二合。食べるものがなかったから、近くの築地川南支川の縁が泥になっていたので、そこに大根なんかを栽培してね。 明日、穫って食べようかなと思っていると、みんな持っていかれてしまってね。商売を再開したのは、昭和21年でした。両隣には、卵焼きの大膳さんと八百屋の妻定さんがあったね」
築地のいい思い出とは、昭和25年から東京オリンピックまでのいちばん景気がよかった時代に尽きるという。 妻の梅子さんが嘉市さんのもとに嫁いで来たのも昭和25年だった。吉江さん夫婦はいまも店の2階で暮らし、築地には愛着があり、ここを離れようと思ったことは一度もないという。
「商売のスタイルが変わったのよ。ここで商売して、自宅を都心から離れた町に構える人が多くなったのよ。築地のいいところは、まず便利だってこと。 下町だから人情も濃いしね。いま、こんなおかずがあるからおいでよなんて声掛け合うの。いまのビルになる前は七輪で魚を焼いていたのよ。 隣近所、順番に七輪が回ってきてね。それで、きょうのおかずはコロッケだよっていうと、コロッケ屋さんに行くというお手伝いさんがみんなの注文をとったりしてね。 ソースがないよっていうと、うちにあるから使いなよっていう具合に、そりゃあ、隣近所、親しみがあったわよ。戸締まり一つにしても、心張り棒をするだけで、よかったものね」
そう言って梅子さんが笑うので、こちらもつられて「心張り棒って、時代劇に出てくるあれですね」と言ってみる。「そうそう、棒を斜めにして戸に当てるあれよ」と再び梅子さんはからからと笑う。
昔は午前4時に開店、昼には閉店していた。休みも戦前は元旦だけで、定休日が二の日と決まったのは戦後のことだった。
「忙しかったね。あの頃は、車なんてなかったから、得意先に品物を届けるのでも自転車の荷台に積んで、竹の皮で包んだおにぎりを持って途中で腹ごしらえしてね。 荻窪、遠くは八王子まで行ったんだよ。一日がかりだったね。自転車の前をトラックが走っていると、その後ろつかまってそのまま走る。らくちんだからね」
吉江さんは当時のことを懐かしそうに語る。最初は「あんまり覚えていないよなあ」と言っていたのだが、次から次へと思い出が甦ってきたのだろう。
祭りもにぎやかだった。祭り好きの先代は波除神社の祭りになると、夢中で神輿をかつぎ、店の前でお菓子の袋詰めを近所の子どもたちにふるまい、そのうれしそうな顔を見ては喜んでいたという。 ポンポンと繰り出される昔の話は聞いているだけでも楽しくなり、当時の情景がくっきりと描かれる。
「うちの裏に紙芝居も来ていて、黄金バッドなんかやっていたね。そりゃあ、子どもたちが大喜びだった。いまのすし好があるところにパチンコ屋があった。銭湯も各町内にあった。 銭湯では情報が集まったね。男湯と女湯、あちらとこちらで声を掛け合って「おい、もう出るぞ」なんていってね。あと、料亭も多かった。代議士がさかんに料亭にやってきた時代だね」
日本橋時代から扱ってきた料理道具も時代の変遷とともに様変わりしていった。失われた道具は数々ある。檜でできた氷の冷蔵庫。 中身がブリキ製の二段構えになっていて、上段に氷を入れて冷やすもの。長火鉢のような形をした二口の七輪もあった。 これは外側にタイルが貼られ、内側が耐火煉瓦になったものだった。ひとつひとつを丁寧に手づくりする職人がいなくなってしまったため、 ほうろう引きのバット、手編みの竹製のざる、竹ぼうきなども失われた道具たちなのである。
今後の場外市場に寄せる期待をうかがうと、吉江さんは「うーん、そうだね魚屋さんが減ったのがいちばん寂しいよね」と言ってから、
「場外が大きく変化したのは、魚が産地直送になってからかな。昔は籠をしょって仕入れに来ていたけれど、車で来るようになってから、雰囲気も変わってしまった。 でもね、ここんとこ、若い人たちが盛り上げていこうっていうので、さかんに宣伝しているから、土曜日もけっこう人が集まっている。これからもどんどん人を集めなきゃね」
70年近くの長い歳月とともにあった嘉市さん、そして梅子さんはいまも早朝から店に出て働く元気な生涯現役なのである。
(平成18年 龍田恵子著)