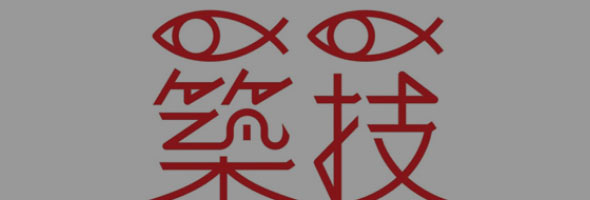築地を知る | 築地昔話館 | 男たちの語り
今も生きる父の教え
小見山順一郎さん(大正15年生・小見山商店)

場外市場にある小見山商店は割箸、包装資材全般を扱う専門店である。小見山さんの祖父は日本橋の経木職人だった。 経木とは、木材を紙のように薄く削ったもので、それに経文を写したことからこの名がついている。 主に松材を使い、鰹節のカンナのようにして、幅が3寸から5寸(1寸=2.54cm)数種類があった。 経木は魚や肉、菓子などを包む資材として、昭和40年代ころまで盛んに使われたものだった。 この経木を問屋へ卸してねぎられるよりは、いっそ店で売ったほうが得策だと考えたのが、小見山さんの父、一郎さんだった。 三越の呉服部に勤めた経験もある明治30年生まれの一郎さんは根っからの商人。 大正12年12月、日本橋から市場通り(新大橋通り)の西側に間口1間奥行き3尺の場所で、折り箱・経木専門店を始めた。
「私が生まれる前のことですが、当時、土地の所有者である佃政の親分が瓦礫を始末してくれれば店を出してもいいよということで、 市場通りに店を構えたと聞いています。現在地の4丁目5番の約12坪に2階建ての家を建て、その後すぐに店もここに移して商売を続けていました。 毎日、忙しかったから、家族そろって食事をしたという記憶がないくらい。菅商店はしもた屋だったので、私はときどきお箸とお茶碗を持ってごはんを食べさせてもらっていましたよ」
小見山さんは大学卒業後、自分の個性をどこで生かしていいのかわからないまま「サラリーマンは決まった金額の中で生活していくが、商人は日銭が入る」と思い、 昭和23年暮れからごく自然に店に入り、父とともに働くようになったのである。
当時は、毎日のように産地に行っては、経木や折り箱や割箸の材料を自分の目で確かめた。 材料を買って職人に渡し、職人を集めてどうやったらいいものができるかを考えた。また、「利益というものを基本的に見直してくれ」と父に言われ、税務署の対応にも追われた。 小見山さんは父から多大な影響を受けたという。
「いい商品を安く売ればお客がついてくる。品物が安くなったら、それだけいい品物に切り替えていく。 たとえば、5円でできるものが4円でできるとようになったとして、父は箸や経木を作っている職人、そのまま4円でできるものにおれは5円出してあげるから、 そのかわりにその差額の1円分をもっと品物をよくしろ。それでもって、お客の信用を獲得すること。それが商売を継続させる唯一の手段だと言うんですね」
昭和40年代に入ってから、人々はスーパーの便利さに飛びつき、小売りは時代遅れとなり、この先は伸びないとまで言われた。 小見山商店でも大手スーパーの消費者に対応するような店に変えたらどうだと言われた。 「父に相談したら、おまえがそういうシステムでやるのはかまわないが、おれはやりたくないと言う。おれは小売り屋で、大手は大手の取引きでやればいい。 末端の消費者は別にして、その中間のわれわれが目的とする商人たちがどこで買っていいのかわからなくなってしまう。 その人たちが残っている間は、その人たちのために品物を提供する。それが小売り屋の務めだと言うんですね。 それじゃ、私も父の言うとおりに、買ってくれる人に対して小売りを徹底させようと決心したんですよ」
小見山さんの父は一定した良い品を売るには、まず第一にお客の信用が大事と言ってはばからず、なるべく売掛けを避けたのである。 売掛けで買う人も現金で買う人も同じ値段というのは不公平だという。また、安売りもしなかった。 安売りをして、たまたまその日に来店できなかった常連のお客さんにはどうサービスするのかと懸念した。 誰が買っても同じ値段を統一させようとあくまで定価販売にこだわったのである。 「昔は割箸でも経木でも中身の数量については・約100膳・・約100枚・と袋に表記していたんですよ。つまり、正確な数ではなかった。 問屋を呼んで聞いてみると、実際には96膳しか入っていないという。それを改めさせたのも父でした。足りない4膳の金を出すからと言い、すべて・正100膳・としたわけです。 それから、お客さんに対しては売り切れだと言ってはいけないと。よかったらこういうものもありますよって、教えて差し上げるんですよね」
父の商売に対する姿勢を間も当たりにして、「商売は自分の目と経験で確かめるしかない」と小見山さんは実感したというのである。 小見山さんが父から引き継いだ「商売の心」は長男の純一さんへと引き継がれていった。 時代の移り変わりと共に、包装資材も様変わりし、ポリエチレンの 進出などは小見山商店の商売を大きく変えるものだった。 しかし、割箸も折り箱も日本の食文化には欠かせないもので、代が変わったいまは、外へ向けて発信し、商売の発展をめざしているのである。
築地で生まれ育った人たちにとって波除神社の祭りは格別である。では、正月というのはどうなのだろうか。 師走は一番のかき入れどきで、大晦日でさえ配達や集金に追われ、明け方近くまで働いていたと聞く。 「元旦になってもみんな寝ていて、朝早くから正月のお祝いをしていられなかった。でも、母親は煮物となます、蒲鉾、伊達巻など、ごく普通のおせちは作っていました。 2日が初荷だから、店の前では挨拶に来るお客さんに振る舞い酒を出していました。11日の鏡開きには近くの銀行でお汁粉を振る舞っていたので、学校の帰りに食べた記憶があります。 やはり、魚河岸は正月よりも、お祭りのほうがにぎやかですよ」
戦前戦後の激動の時代から高度成長時代を経て平成へ。常に築地と共にあった小見山さんもまた生涯現役なのである。
(平成18年 龍田恵子著)