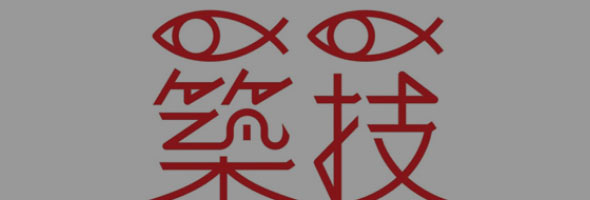築地を知る | 築地昔話館 | 男たちの語り
少年の目に映った古き佳き築地
荒井重雄さん(昭和9年生・福屋)

戦前、荒井さんの父は現在の石橋商店が建っている場所に麩屋を開いていた。神奈川県出身の母が父のもとに嫁いだのは数え二十歳、 結婚式の翌日に日本髪を結ったままで店に出たところ、近所の人たちに「おお、あの子はお嫁さんの格好で店に出ているよ」とからかわれたが、 当時、この母の姿は近所の人々の目に焼き付いたものだった。父は店の奥で麩をつくり、母は店頭で麩を売った。 荒井さんの戦前の築地の思い出といえば、小学5、6年生のころに遡る。興味深いエプソードは数々ある。
京橋信用金庫の会長だった金子さんの奥さんは元は京都の舞子さんで、とても美しく人目をひく女性だった。いつも決まった時間にお供を連れて場外市場にあった築地湯へやってきた。 「ぼくら近所の男の子は築地湯で奥さんが脱いだ草履をそろえてあげると、毎度、おおきにはばかりさんと言うのでそれが面白くて、奥さんがやってくるたびに草履をそろえていました。 なんていうか、ませた子どもだったんですね。それから、場外に大六という大きな店があって、そこの悦子さんというお嬢さんが乗馬をやっていて、自宅から馬に乗って築地に遊びに来ていたんですよ。 ときどき、店の者に馬を洗わせていたのを見かけましたね。いま思えば、ほんとうに不思議な光景でした」 それは初めて聞く話だった。若い女性が馬に乗って場外市場に来るなど現代では想像もできないが、確かに馬が荷車をひいてゆったりと歩いていた時代はあったのである。
戦時中、荒井さんは疎開していたが、昭和20年の暮れに疎開先から帰ってきたとき、この場外には営業している店が数少なかったという。 当時の強烈な思い出は、やはり築地にいたアメリカ進駐軍の姿である。アメリカ兵にとって築地本願寺は珍しい日本の建物だったのだろう。 そして、日本で元気でやっていることを本国にいる家族に知らせるために、本願寺で記念写真を撮って送ったという。 「その写真にぼくら近所の子どももいっしょに入れというのですよ。わけもわからず写真におさまりましたね。 例のごとく、進駐軍にはガムやチョコレートをもらったりしました。ぼくらはただただ興味深かったです」
食糧難の時代、たまたま分けてもらった平貝を売ったり、またその貝のひもを入れて銀シャリでご飯炊いてもらって食べたら、驚くほどおいしかったという。 また、現在の立体駐車場になっているところが昔の法務省で、そこを進駐軍が接収していた。明日から新円になるというときに旧円がばらまかれた。 「旧円を拾って、姉に万年筆を買いました。残りの旧円でみかん買った記憶がありますよ。それで、新円になった初日にはわかめを売りました。 その日に1万円が売れた。みんなうらやましがった。あのとき、旧円が箱にたくさん入って、蓋がしまらないほどでした。 旧円は貯金しました。終戦のとき、旧円で10何万円もっていた人はたくさんいましたよ」
平成17年7月1日の70歳の誕生日の前日を区切りとして、「70歳で店を閉める」と宣言した。閉店については惜しむ声も多かったが、荒井さんの現役引退の意志は固かった。 文字どおり6月末日まで働いて閉店にしたのである。そこで、鳥藤の社長が「この街で元気なうちに辞める人というのは初めてだから、みんなで送る会をしよう」と提案。 有志一同が企画した送る会では、出席者全員が荒井さんの思い出を3分間スピーチしてくれた。 記念として「福屋」の看板を自宅に持ち込むことは無理だったことがわかっていた有志一同は、ミニチュア看板を制作して新井さんにプレゼントした。 荒井さんは場外市場の仲間たちの気持ちをうれしく思った。
現在、荒井さんは日本橋浜町に住んでいるが、築地への思いは変わらない。 「これからの場外市場は、素人もプロも買える魚屋さんがどんどん増えれば、このまま商売続けていけると思うんですよね。だから、みんなで頑張ってほしいです」
(平成18年 龍田恵子著)