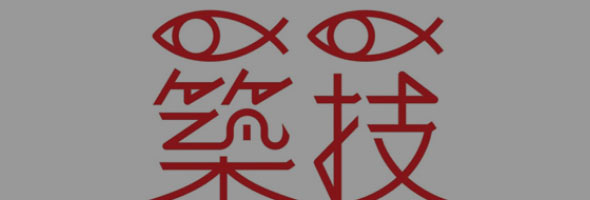築地を知る | 築地昔話館 | 男たちの語り
強気の商売をしていて、活気がありました
神崎祐二さん(昭和10年生・味の浜藤)

現在、漬魚や練り製品、干物、魚卵、鮭、珍味などを扱い、百貨店や駅ビルで4ブランドを展開している「味の浜藤」の歴史は大正時代にさかのぼる。
初代の森口二三が大正14年に生地の福岡県から上京し、小田原町においてサラシ鯨を百貨店などに納める商いを起こしたのが始まりだった。 やがて、海産物に手を広げ、昭和2年に明石町(現在の塩瀬総本店がある場所)に工場を新築移転した。昭和9年に場外市場に築地本店を開店し、3年後には月島本社工場を新築移転した。
3代目社長・森口一氏の叔父に当たる取締役常任相談役の神崎さんは福岡の出身だが、昭和28年に東京の大学に入学し、月島工場の2階にあった寮から大学に通っていた。 卒業後は百貨店で2年間の勤務を経て、昭和34年に味の浜藤に入社した。
「私は仕入れを担当していました。当時の東京は築地以外に市場がなかったので、市場はとても繁盛していましたね。 河岸の中も仲買しかいなかったし、もちろん、素人のお客さんのいない時代です。昭和28年から34年ころまで、浜藤の築地店はいまの売り上げの10倍もありました。 納品というシステムがなかったので、毎日、関東一円から築地に集まってきたので、大混雑です。 場外には食堂は数えるほどしかなかったし、場内にあった食堂は河岸で働く人や買い出しに来る人たちのための福利厚生施設です。 吉野屋さんの牛丼が安くておいしくて、よく食べたものです」(写真はかつての浜藤明石町工場。左の塔は、今も残る聖路加病院である。)
全国的に練り製品が最も売れた時代、東京のいたるところにおでん屋があり、小売店も多かった。 メカジキ、サメ、グチ、ハモ、小魚類など生の魚が大量に入り、職人たちの手作りだった。 浜藤の製品全体の37%が練り製品で、それ専門の職人も40人~50人いたという。 また、当時の東京都では練り製品を製造するのに使用された約100トンの排水を処理できるシステムも万全だったのだ。
 浜藤に画期的な展開が訪れたのは昭和26年のことである。渋谷の東急百貨店東横店に東横のれん街が誕生するが、浜藤は百貨店初のテナントとして出店したのだ。 実は東横のれん街のその場所は、ちょうど東横線ホームの下で砂利や枕木などの道具置き場になっていた。 広いスペースを放置しておくのはもったいないということで、浜藤の初代が音頭をとり、有志を集めて「何とか利用できないものか。 それには何をしたらいいのだろうか」と検討を重ねた結果、「都内の有名店を1カ所に集めたら、お客さんが喜ぶのではないか」というアイデアが生まれた。 当時の渋谷は「渋谷村」と呼ばれるほど、まだ街が整備されておらず、「あんなところに店は出せない」などの反応もあった。 しかし、浜藤の練り製品をはじめ、和菓子、佃煮などを扱う店が出店を申し出て、15店舗でスタートしてみるとたちまち評判を呼んだ。 次から次へと出店数がふえ、全国の名物、ふるさとの味が集められた。浜藤では、のれん街で販売する製品を夜中に作って、新鮮なものを朝に出荷した。 東横のれん街は百貨店にテナントとして販売店が入る形式のはしりなのである。
浜藤に画期的な展開が訪れたのは昭和26年のことである。渋谷の東急百貨店東横店に東横のれん街が誕生するが、浜藤は百貨店初のテナントとして出店したのだ。 実は東横のれん街のその場所は、ちょうど東横線ホームの下で砂利や枕木などの道具置き場になっていた。 広いスペースを放置しておくのはもったいないということで、浜藤の初代が音頭をとり、有志を集めて「何とか利用できないものか。 それには何をしたらいいのだろうか」と検討を重ねた結果、「都内の有名店を1カ所に集めたら、お客さんが喜ぶのではないか」というアイデアが生まれた。 当時の渋谷は「渋谷村」と呼ばれるほど、まだ街が整備されておらず、「あんなところに店は出せない」などの反応もあった。 しかし、浜藤の練り製品をはじめ、和菓子、佃煮などを扱う店が出店を申し出て、15店舗でスタートしてみるとたちまち評判を呼んだ。 次から次へと出店数がふえ、全国の名物、ふるさとの味が集められた。浜藤では、のれん街で販売する製品を夜中に作って、新鮮なものを朝に出荷した。 東横のれん街は百貨店にテナントとして販売店が入る形式のはしりなのである。
浜藤の築地店は場外市場の歩みとともにあった。いまでこそ、場外にはコンクリートの建物が多くなっているが、戦前戦後は木造3階建てが主流だった。 しかし、建物の老朽化や場外市場の活性化などを考慮して、再開発計画が持ちあがったこともある。神崎さんは当時のことを振り返る。 「昭和42、3年でしたかね。国と東京都が主体となって場外市場にビルをつくろうという計画があったんですよ。 準備委員会も発足されました。ところが、賛成が8割だったのですが、反対運動がおきて解散しました。そのころから、築地にビルが建ち始めていったのです。 いまでは、6、7割がビルになってしまいました。あのとき、再開発のビル建設が成功していれば、市場移転問題も起きなかったと思いますね」
創業82年の味の浜藤。初代が小田原町で始めた商いは明石町、月島、築地に根を張りながら“本物の味”を追求し、全国に販路を広げてきた。 そして、神崎さんは半世紀以上もの長きにわたって浜藤とともにある。 「佃大橋、中央大橋もなかったころ、佃の渡しで築地に通いました。勝鬨橋が上がっていたのも、当時の特徴でした。 リヤカーや三輪自動車が走っていたころが、いちばん市場が繁盛していたんじゃないかな。みんな、強気の商売をしていて、活気がありました」 神崎さんの話を聞きながら、古き良き時代の風景が蘇るのだった。
(平成18年 龍田恵子著)