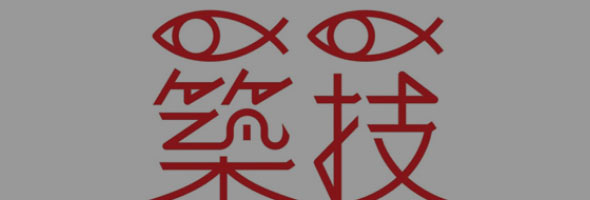築地を知る | 築地昔話館 | 女たちの語り
いまは戦いすんで、日が暮れて
北島初枝さん(大正6年生・北島商店)

先代の北島文八さんは昭和九年に九州は有田焼きの産地から上京し、 現在と同じ場所で有田屋という瀬戸物屋をはじめた。 浅草生まれの初枝さんが文八さんのもとに嫁いだのは昭和十三年四月のことである。 当時、店の前の通りは瀬戸物通りと呼ばれていた。 昭和十七年、北島さん一家は茨城県佐和に疎開した。 そして、小さな三人の子供を連れて戻ってきたのは四年後のことである。 そのとき家を一軒売り、その金でまきと米を買って持ってきたという。 「疎開するときに店は人に貸していました。帰ってきてから半分をそのままにしてお いて、わたしたちは六畳の方に入れてもらいましたよ。 戦争中、店の屋根に見張り台をこしらえていたらしくて、そこから雨が漏るものだ から傘をさして寝たものです」 と初枝さんは当時を振り返る。
店をたたんで疎開したので瀬戸物はすでになく、一から商売をはじめなければならな い。しかし、夫の文八さんが病気になり、その間、初枝さんは実家の父に子守を頼ん で働くことになる。 まず、のしいかは家の中で袋詰めをして売り、次に昆布を売った。 「昆布なんかは統制品だったので、よく警察に怒鳴られました。おじいちゃんが子供 のお守をしているときに警察が来ると、わたしは逃げちゃったこともあるわね。 そうすると、おじいちゃんが怒られるんです」 あわてたり恐縮したりする"おじいちゃん"の顔が目に浮かぶようである。
最初は店の前の通りには客がやって来なかったので、 人通りの多い通りに売場を探した。 「マルミ屋さんの軒下を三尺借りたんですよ」そこにするめと昆布を並べた。 それが売れるようになると、今度は落花生や飴なども売るようになり、 その仕入れは日暮里まで出かけた。 ぶっきり飴の一斗缶が入った「ずっしりと重い」リュックサックを背負い、 ぎゅうぎゅう詰めの満員電車に乗って帰ってくるのだ。 電車に乗れないときは途中から歩いたこともあったという。
そうした日々の積み重ねがあればこそ、明日への希望につながっていくのだろう。 そのうち品物は配達してもらえるようになり、徐々に商売のかたちが出来上がってい く。そして昭和二十二年、乾物、缶詰、菓子など扱う品目が増えてくるころには、夫 の病気も回復していた。 築地に活気がよみがえる昭和二十四、五年のころ、店の従業員の給料は三千円(住込 み、三食付)と安かったが、新聞で従業員を募集するといくらでも応募があり、多い ときなどは二百人を超え、選ぶのにも苦労したという。 また年の暮れともなると、通りは人であふれ、前へ進むにも進めない、身動きがとれ ないほど混雑した。 「築地にいちばんお客さんが集まったころですね。病気しても店に引っ張りだされる ほど忙しかった。まだ一万円札がなかったから、たいへんでした」
忙しい日々が続く中、「ふだん、三人の子供たちは人まかせだった」ということが、 初枝さんにとっては仕事の苦労よりもつらいことだった。 日中は子供たちが学校から帰ってきた事を確認する程度で、ほとんど話もできない。 夕食後、風呂に入ろうというころに、やっと三人の子供たちと向き合えるのである。 しかし、その忙しい中でも父兄参観日などにはどうにか時間をやりくりして学校に行 き、授業を受ける子供たちの姿を見ることができた。 また日曜日に家族そろって「不二家」へ食事に出かけることもあり、それが一番うれ しい親子のふれあいだったという。
「戦後は生きるために無我夢中でした。 いまは戦いすんで、日が暮れてという感じです」と初枝さんは言う。 戦後の築地は、日本中どこもそうであったように、混乱から抜け出て白分たちの生活 をなんとか復興させようとする人々の様子に象徴される。 当然ながら、その時代がなければ、都市が大きな変貌を遂げる昭和三十年代はやって 来なかった。
そこで印象に残っている"戦前の築地"についてたずねてみた。 「昔は料亭がたくさんありまして、そこのきれいなお姐さんたちが朝の十時ころうち の向かいにあったお風呂屋さん(築地湯)に入りに見えるんですよ。着流しで下駄 をカラコロ鳴らせてね・・・。すると、うちの店の者たちが、わざわざ女湯の入口 が見えるような所で瀬戸物の荷物をといたりしていました」 そんなのんびりとした時代もあったのである。 新しいものができる一方で、古いものが消えていく。 淋しいことには違いないが、初枝さんは昔を思い出して感傷にひたることはない。 「負けちゃいけない!」という気持ちで生きてきたいま、悔いはない。
生涯現役。週の半分は店に出て働くが、あとの時間は好きなことをして過ごす。 現在、孫が七人に曾孫が二人。しかし、驚くほど若い。目を凝らして見たのだが、 ほとんどしわがない。 「あっというまに時が過ぎていったという感じですね。いまは自分の人生です。 これからは第三の青春だと思っています」 そういって初枝さんは笑った。
(平成6年 龍田恵子著)