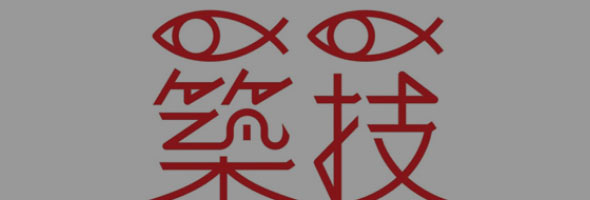築地を知る | 築地昔話館 | 女たちの語り
終戦後、気楽に商売してみて
佐藤喜三子さん(大正6年生・太平山)

新大橋通りに面して床店がずらりと並ぶ。 そこを場内市場の方向へ歩いていく中ほどに「太平山」はある。 昭和二十一年十一月に創業して以来、"酒とビールとおでん"一筋の店である。 秋田の蔵元から取り寄せる太平山という酒がそのまま店名になった。 当時、"太平山"を扱っていたのはここ一軒だけだったが、 "太平山"が出回りはじめたころから、酒は"伏兄の富翁"に切り替えた。
店内に入ってまず目につくのが「太平山」の古びた看板。 これは開店祝いとして当時の四丁目町会から贈られたもので、 初代会長だった萩原銀弥をはじめ、秋山銀次郎、北田喜定、大野義一、池田憲次郎、 山野井弥之助など四丁目町会の人たち、十六人の名前が刻まれている。 五十年近い歳月を経たいま、健在なのは山野井さんだけとなってしまった。 店主の佐藤喜三子さんは七十七歳、現在も朝の四時半には店を開ける。 まず、河岸でひと仕事を終えた威勢のいい男たちがやって来る。 おでんを肴にコップ酒でキューッと一杯やる。 渇いたのどにはビールもいいだろう。 これがうまい。 時間帯によって客の顔ぶれも変わってくる。 「うちは酔っ払いがいないわね。三杯以上は飲ませないことにしているのよ」 初めて見る顔もある。 スーツ姿の客もやって来る。 「東京には出張で来たから寄ってみた」という人も多いという。
ところでこの床店が並ぶ一帯、昔は墓場だったが、関東大震災で焼け野原になった。 そのときここにバラックを建てたのが、この辺りを仕切っていた佃政の親分である。 当時、この親分の名前を知らない人はいないといっていいほど、大きな力をもってい た。特に昭和九年、佃政の親分が亡くなったときの葬儀についてはすでに何人かの人 に聞いているが、この築地の昔を知るためにも欠かせない逸話のひとつになっている のである。 「わたしは親分が亡くなったときはまだ築地には来てなかったから実際の葬儀は見て いないけど、親分の三十周忌が帝国ホテルであったんですよ。そのとき、葬儀の模 様を映したフィルムを見ましたけれど、それは盛大でしたね。日本中の親分が集ま ったといいますから、行列が自宅から本願寺までずうっと続いたんですよ」
喜三子さんは人形町で生まれた江戸っ子である。 昭和十四年、夫の万吉さんと結婚し、戦前は神田神保町で「江戸善」という店を商っ ていたが、五年間の疎開を経てここに「太平山」を構えたのである。 「この辺りは間引き疎開で家を壊されて、終戦のときにバラックが建てられたのよ。 この建物自体はそのときのままなのね。五十年も持ちこたえている。人が絶えずい るからもっているんでしょうね。うちが入る前はお花屋さんだったそうです」 当時、店の権利金が四十万円、改装にかかる費用などを加えると百万円近くの金が必 要だった。疎開先の桜台の家を売った十二万円と夫の友人に借りた六十万円などをか き集めて、なんとか店を持つことができたのである。 「借りたお金は一年足らずで返しちゃったわね。だから、借金があるっていうのはい いことなのよ。励みがつくっていうのかしらね」 終戦から二、三年後、ちょうど街全体に活気が出てきたころでもあった。 大勢の人たちが築地にやって来た。 「うちは最初からおでんを売ったのよ。はじめるときは、それこそシューマイやラー メンも売るつもりでいたんですけど、とにかくお客さんが多くて、おでんだけで商 売するよりなかったわね。それに他の店で売っているものを、うちでも売ろうとい う気にはならなかった。商売をする以上、その辺はわきまえなきゃいけないと思うのね」 昭和二十一年から二十五年ころまでがいちばん活気に満ちていたという。 だから、朝の四時半から夜中まで働いた。 除夜の鐘を聞きながら家路についたこともある。 「お客さんもいまとは気構えがちがったわね」と喜三子さんはいう。
これまでで一番つらかったことは? 月並みな質問を向けてみた。 「つらかったことね……あるといえばあるし、ないといえばない。そんなもんよ。 つらいことなんて早く忘れてしまうものよ。商売をしていてもお客さんに神経なん て使わなかった。飲食店をする上で大事なのはまず清潔であること。それさえ気を つけて、あとは気楽にやっていました」 夫の万吉さんは十七年前に亡くなった。 十一歳上だった万吉さんについては 「とにかく道楽者だった。それこそ小説になるような経験をしたわよ」 と喜三子さんは笑いながら次のように語ってくれた。 「外面がよくて、内面が悪い人だった(笑)。白黒はっきりした性格。おかずなんか でも、前の日の残り物は決して食べなかった。結婚して五年後に大きな夫帰喧嘩を したとき、友人が仲裁に入ってくれたことがあったわね。でも、子供に好かれる人 だったですよ。まあ、とにかく賭事が好きでね。いつだったか、負けてオーバーま で取られたことがあったんだけれど、そのとき夫は進駐軍がくれたチョコレートと 交換したなんて言い訳するのよ。純情なところもあった人でした」
万吉さんは酒もよく飲んだ。しかし、病気になってからはピタッとやめてしまった。 長い療養生活のあとは自宅療養となり、万吉さんは途端にわがままになったという。 「点滴が落ちるのが遅いから、早くしろ」といっては喜三子さんに甘えた。 そういう夫に四十年近く連れ添った。 「縁あって夫帰になったと思わなければならないのよ。 いろいろあったけど、楽しい人でしたよ」 喜三子さんは豪快に笑うのである。
店と白宅の往復にはタクシーを利用している。 「女ってお酒飲んで遊ぶってこともないから、もったいないとは思わない。 お金はきれいに使うためにあるのよ」と屈託がない。 ところが今年の四月の交通安全週間、タクシーに乗っていた喜三子さんは、追突事故 が原因で首、足などにけがをした。そのときの運転手の対応が「お客さん、料金タダ にしておきますよ」というひどいものだった。 これにはさすがの喜三子さんも腹が立ったという。 「こっちはそのタクシーに乗っていて怪我をしたのに、運転手はお客より車のほうが 気になるんですものね。なんでも保険でかたづくと思っている人が多い。本当にあ きれてしまうわよ。いまの世の中、人情が足りない。殺伐としていますね」 いまも後遺症はあるが、 「口がきけるだけでもいい。毎日、ここに来れば元気になるもの。 やっぱり、街の商人っていいわよ。五十年もいると、いろいろなことがあります。 ここはまさに人生の縮図です」
気ままに店に出て、余暇には好きな旅行を楽しむ喜三子さんなのである。 店内は開店当時とほとんど変わっていない。 カウンターは一枚板のがっしりしたもので五十年近い歳月を刻み込み、その表面はみ ごとな黒光り。木の椅子も昔のままだ。氷を入れて冷やす木製の冷蔵庫は、知り合い の棟梁が改造してくれて食器棚に変わった。立て付けの悪い戸も修理を重ねてなんと か持ちこたえてきた。 それらの一つひとつを眺めていると、五十年前の時間がすぐそこにあるような気がし てくる。
(平成6年 龍田恵子著)