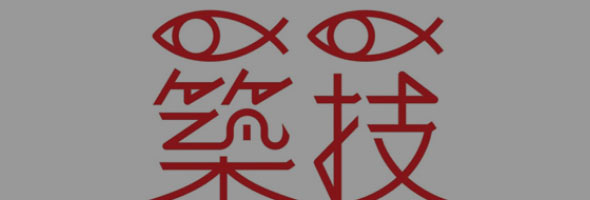築地を知る | 築地昔話館 | 女たちの語り
働く楽しさを知ったあの混乱期
岩附まつさん(大正7年生・八百金)

八百金は日本橋で妻物を商っていたが、大震災で魚河岸とともに築地に移転した。 その頃、店を出したのは魚河岸のすぐそばで、自宅は現在地と同じ築地六丁目にあった。 埼玉の農家で生まれ育ったまつさんが八百金に嫁いだのは、昭和十五年のことである。
親戚の人の世話だった。まつさんは妻物屋というのが何を売っているのか全く知らず、 嫁いできて初めて商売の内容を知り、驚いたという。 すぐに戦争がはじまった。 戦争中は強制疎開があって商売はできなかった。
終戦後、夫の峯一造さんは共同で店を借りて商売をしていたのだが、 昭和二十一年にまつさんは現在の四丁目8番に店を出す。 そこはもと飲み屋で、客として通っていた知り合いのおまわりさんから、 店を売りに出すという話を聞き、それでは買おうということになった。 一人の一ヵ月分の生活費が百円という時代、その店の権利金は二万円だった。 「そんな大金、なかったわよ。それで田舎の父に借りに行ったの。 ところが、父は貸してくれなかったのね。 親子といっても他人なんだなと、悔しくて三日も泣きました。 でも、あとで考えてみたら、そのとき父は貸さなくてよかったのよ。 もし、貸してくれていたら、わたしはグズになっていたと思うのね。 貸してくれなかったから、わたしは気が強くなって、 一生懸命に働くようになったのでしょう」
人生、なにが幸いするか、まったくわからない。 まつさんは毎日、夜が明けるのが楽しみだったというくらい 仕事が好きになり、がむしゃらに働いたのである。 当時、八百金のまわりには向かいの珍味屋しかなかったので、客も少なかった。 まつさんはまだ夜が明けないうちに闇市に行き、 三箱分のわさびを唐草模様の風呂敷に並べて売った。 頭には防空頭巾をかぶっていた。 それがわさびを売るはじまりである。 わさびは信州から新宿に届けられるのだが、夜のうちに電車に乗って買いに行った。 一箱二百円だった。 わさびは毎日一時間ほどで売れ、うれしいほど儲かったという。 そしてわさびを売ったあとに、店を開けるという忙しい毎日だったのである。 「でも、おもしろかった。ああいうときがもう一度来ないかなと思うわよ」 とうれしそうに当時を振り返る。 そのようにして混乱期を生き抜いたまつさんは、 いつの間にかすっかりたくましくなっていたのである。
お父さんが亡くなったとき、「わたしを一人前の女にしてくれてありがとう」と まつさんは父の遺影に向かって、何度も礼を言ったという。 「でも、娘たちに言われたのよ。 お母さんは女としては一人前かもしれないけど、母親としては失格ねって。 どうしてって聞いたら、学校で運動会があってもなにがあっても 来てくれたことがなかったっていうのよ。 そりゃあ、そうよね。 忙しかったもの」
終戦後しばらくしてから、もともと体の弱かった峯一造さんは 寝たり起きたりの生活が続き、まつさんは夫の分まで働いた。 朝三時に起きて買い出しに行く。 いったん家に帰り、食事の支度をしてから店に出て、昼まで働く。 店を閉めたあと、今度は家で仕込みに追われる。 そうやって、息つくひまもなく寝るまで働いた。 昭和三十年に峯一造さんが亡くなり、女手ひとつで二人の娘を育てていくことになる。 「商売の方は儲かっていたから、お金には困らなかったけれど、 使用人にはずいぶん泣かされましたね。 女だから馬鹿にされるのかと、お便所に入っては泣いていたわね」 過ぎてしまえば、それも昔のことである。
いま、まつさんは長女の高橋さん夫婦に店をまかせ、日中は愛犬と散歩したり、 洗濯したりと、のんびり過ごすことが多い。 作家の森田誠吾氏が昭和六十年に直木賞を受賞した「魚河岸物語」は、 築地を舞台にした人々のふれあいを描いた作品である。 その中の〈門跡橋〉に登場する八百松のおかみさんというのは、 実はまつさんがモデルになっている。 森田氏は銀座の生まれで、聖路加国際病院に通院していたころに 築地界隈を散策し、八百金にもたびたび顔を出していた。 森田氏が築地に寄せる眼差しはどこまでもやさしく、その思いは深い。 「本ができたよって、持ってきてくれたのね。 それからしばらくして、直木賞を受賞したんですよ。 店の前で森田さんもいっしょにみんなで"バンザイ"しました。 『魚河岸物語』を読んで、わたし泣いちゃったわよ」 まつさんにとっては忘れられない思い出のひとつなのである。
(平成6年 龍田恵子著)