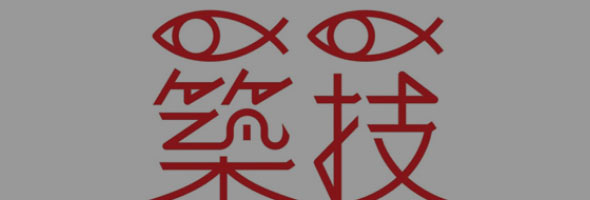築地を知る | 築地昔話館 | 女たちの語り
忙しいけれど、にぎやかな時代
秋山和子さん(昭和11年生・秋山商店)

鰹節問屋の秋山商店は大正5年に初代秋山銀次郎の個人商店として芝でスタートし、関東大震災後に日本橋の魚市場の築地移転をきっかけに、現在地の場外市場に店を移した。 当時、秋山商店は鰹節専門店の先駆けであり、銀次郎は昭和初期に削り節を日本で初めて商品化し、さらに機械による糸がき「糸賀喜」を編み出した。 このメジマグロだけを使った美しい色合いの糸がきは大変な評判を呼んだのである。
昭和30年、2代目・秋山咏三さんのもとに嫁いだ和子さんはいまも水曜日以外の営業日の午前9時半から午後1時まで店に出ているという、とても元気な女性だ。 時にユーモアを交えて語る昔話につい引き込まれた。
明石町で生まれた和子さんの生家は現在の「治作」の前にあった。 「治作の横から水が流れて船だまりになっていたのよ。うちの窓から見ると、多いときで10~15雙の舟がつながれていました。 当時は舟で生活する人たちがいて、うちの窓からは舟の上で猫や犬を飼っているのが見えたわ。いまは埋め立てられて公園になってしまったので、風景はがらりと変わってしまいましたね」
和子さんの子ども時代、女の子の遊びといえば、おはじき、おてだま、まりつき、ゴム跳び、着せ変え人形、ままごと遊びなどがある。 和子さんは人形の布団や箪笥、着物、ちゃんちゃんこ、座布団、ゆかたなど一式が入った箱をふろしきに包んで友だちの家に遊びに行った。 箱を広げると人形の家になり、そこに着物の入った箪笥を並べ、布団を敷き、人形の小さな世界が出来上がる。 和子さんは祖母や叔母が家に泊まりにくると、人形の着物を縫ってもらったそうだ。また、元気よく外へ飛び出して遊んだ。聖路加国際病院の空き地、勝鬨橋を渡って月島3号地などへも出かけた。 「当時は勝鬨橋が開閉していたころで、橋桁が上がると閉じるまでに20分ほど待たなければならなかったのね。ああ、いそがないと3時のおやつに間に合わないわ、なんてこともあったわね」
和子さんの父は魚河岸の仲買で、母も早朝から帳場に出ていて忙しく、お手伝いさんが和子さん兄妹の朝食と弁当を作ってくれた。 母の手作りのお弁当を食べた記憶はない。また、家族といっしょに出かけることもあまりなかったが、父が持っていた和船に乗って、 両国の川開き(花火大会)やお台場へ行ったことなどが思い出されるという。台場は引き潮になると、かれいやしゃこが採れ、満ち潮になるとボラが採れた。 「妹と二人で手ぬぐいを広げてすくうとあみが簡単に採れて、バケツいっぱいになったんですよ。たまに土左衛門も浮いていて、こっちはまだ子どもだったからあまり怖いとも思わなかったわ」
無邪気な子ども時代から一転して、戦時中の話をうかがった。一時、和子さんは家族とともに浦安の別荘に疎開していたが、 東京よりも先に浦安が爆撃されたというので母と兄は浦安に残り、妹といっしょに埼玉県の父の実家に預けられた。終戦後は浦安に戻ったが、召集されていた父が捕虜になり、消息が途絶えた。 ところが、ある日、「たずね人の時間」というラジオ番組で、抑留者が舞鶴に帰ってくるという情報を知った。翌日、参謀本部に行ってみると、父の生存がわかり、家族で父の帰りを待ったのである。 「当時、わたしは9歳で、父が浦安の別荘に帰ってきた日のことをはっきり覚えています。リュックをしょった父はがらがらにやせていました。庭にゴザを敷いて、そこで服を脱いでからお風呂に入ったのね。 そして、父に背中を流してくれといわれて、へちまで父の背中をこすると、なんと皮膚がへちまにくっついてしまうのよ。どういうことかというと、それだけやせて皮膚がたるんでしまっていたのよね」 9月、新学期が始まった。掲げられていた天皇皇后両陛下の写真が外され、先生の指示で教科書の不具合な箇所はすべて墨を塗って消した。和子さんは子ども心に世の中が大きく変わったことを感じたのである。
昭和30年、和子さんは縁あって秋山咏三さんと結婚した。当時の秋山商店は三階建ての母屋の1階が店舗になっていて、その裏には離れと倉庫があった。 和子さんの1日の仕事は、住み込みのお手伝いさんよりも早く起きて、電気をつけることから始まった。 「毎日、忙しかったですよ。鰹節は結婚式の引き出物にすることが多かったので、よく売れました。急きょ、追加の注文が100なんてこともしょっちゅうあってね。 急ぎはバイクで配達。結婚式の引き出物に鰹節を使ったけれど、法事には鰹節を使わなかった。どうしてかというと、生臭(なまぐさ)だから。 先代は削り節を始めた人でしたけれど、当時の料理屋の板前さんにはプライドがあって、節を買ったものです。板前さんが削り節を使うのはレベルが低いといわれていたのよ。 でも、板場の煮方さんは削り節のほうが楽だから、『すみせん。削ってください』なんていって、こっそり削ったものを持っていったわね。実際、鰹節を手で削るのはとても時間がかかるし、疲れるものね」 そう言って和子さんはおかしそうに笑った。
こちらも子どものころは鰹節を削らされた経験があり、やたらと手が疲れたことを懐かしく思い出すのである。 店に住み込みの従業員が7~8人もいた時代、休みは22日の1日だけで、その朝になるとみんないっせいに遊びに出かけた。 それを見た先代が「休みは体を休める日でないか。遊びにいってどうする」と言ったものだった。 「義父に言わせると、22日が休みになったのは雨が降ることが多くて、商いに向いていないからってことになるのよ。大笑いよね。 みんな休みが楽しみだったのよ。月1回だった市場の休みは、2日と12日が加えられて月3回になったんですよ」
さらに、従業員を巡る面白いエピソードがある。全国各地から集まった従業員たちは食べ物のことで喧嘩になった。例えば、鰹の刺身。 奄美大島出身の人は酢みそにつけて食べるが、新潟出身の人は醤油で食べる。どちらも郷土の味を絶対だと思っているから譲らない。食文化の違いで喧嘩になることもたびたびだったそうだ。 和子さんが語った生まれ育った明石町、そして嫁ぎ先の秋山商店から眺めた築地。忙しいけれど、にぎやかな時代の話は尽きることがなかったのである。
(平成19年 龍田恵子著)